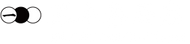将棋駒台・駒箱の選び方


将棋駒台の選び方

「駒台」とは?
「将棋」という競技の大きな特長の一つに、「奪った(取った)駒を自分の駒として使うことができる」というルールがあります。
盤上に無い駒を使えるのですから、「自分が何の駒を何枚保有しているのか?」を公開しなければならないと定められています。奪った(取った)駒を相手が見えない場所に置いたり、手の中に握ったままにしたり、隠したりする行為は「反則」になります。
ですので、対局中に相手から奪った駒は、将棋盤の横の「駒台」という台の上に置いて両者が確認できるようにしなければなりません。
盤上に無い駒を使えるのですから、「自分が何の駒を何枚保有しているのか?」を公開しなければならないと定められています。奪った(取った)駒を相手が見えない場所に置いたり、手の中に握ったままにしたり、隠したりする行為は「反則」になります。
ですので、対局中に相手から奪った駒は、将棋盤の横の「駒台」という台の上に置いて両者が確認できるようにしなければなりません。

「駒台」は、将棋盤の横に対局者それぞれ1つずつ、2枚1組で使用されます。
通常、対局者の右手前に置いて使用しますが、稀に左側に置くこともあるようです。
通常、対局者の右手前に置いて使用しますが、稀に左側に置くこともあるようです。
駒台の歴史
駒台の歴史には諸説ありますが、駒台が一般的に使用され始めたのは明治の末期頃からと、割と最近のことのようです。それ以前は、駒箱や懐紙を駒置きとして使用していたようです。
駒台での駒の並べ方
駒台への駒の並べ方に決まったルールはありませんが、見やすさと美しさから多くの場合は逆扇状に並べられています。
これは、駒が上部へ細い形状のため、駒を辺で合わせて並べると自然と逆扇状に並ぶからです。
これは、駒が上部へ細い形状のため、駒を辺で合わせて並べると自然と逆扇状に並ぶからです。


駒台の高さ
駒台の高さは、見やすく、使いやすく、対局の邪魔にもなりにくいという理由から、将棋盤の天面の高さよりも駒1枚分の厚さ(約5~10㎜)程度低い駒台が一般的です。

駒台の天面(駒を置く面)のサイズ
駒を置く天面のサイズは、4寸×4寸(約12cm角)が通常のサイズです。


価値・価格について
駒台は、木材を使用して作られるのが一般的です。
駒台の材質は、「盤より少し暗い色のものがよい」とも言われますが、最近ではお好みによって好きな素材を選ばれる方も多いようです。
人気の高い素材としては、御蔵島産の島桑や屋久杉、榧、欅などが挙げられます。その他に、銘木の杢の入りの駒台も人気です。
また、駒箱と同じ素材の駒台を揃える方もいらっしゃいます。
駒台の材質は、「盤より少し暗い色のものがよい」とも言われますが、最近ではお好みによって好きな素材を選ばれる方も多いようです。
人気の高い素材としては、御蔵島産の島桑や屋久杉、榧、欅などが挙げられます。その他に、銘木の杢の入りの駒台も人気です。
また、駒箱と同じ素材の駒台を揃える方もいらっしゃいます。




駒台には大きく、脚付盤用と卓上盤用の2種類があります。この2つは、盤面の高さに応じて作られるため、形状も異なります。
脚付盤用の駒台
脚付盤用の駒台は、多くの場合盤面までの高さが高くなるため、駒台自体にも脚の着いた駒台が使用されます。脚付駒台には、脚が1本の1本脚と4本の4本脚の2種類があります。1本脚は見た目がシンプルでスマート、4本脚は少し凝った作りで豪華な印象です。


卓上盤用の駒台
卓上盤用の駒台は、側面や底面に飾り彫を施した豪華なものや、面取り(辺を削って手触りや見た目をよくしたもの)のみを施したシンプルな駒台などがあり、製作者によっても様々な種類が存在します。



将棋駒箱の選び方

「駒箱」とは?
駒箱は駒収納用の木製の箱のことです。多くの場合、購入時には、駒は立方形や平型の桐箱に収納されていますが、お好みよって銘木製の駒箱を誂える場合があり、その際に使用される駒収納用の木箱が「駒箱」です。
木材の素材や色、形状にこだわるなど、駒箱選びも楽しみの一つと言えます。
木材の素材や色、形状にこだわるなど、駒箱選びも楽しみの一つと言えます。




価値・価格について
駒箱は、木材を使用して作られるのが一般的です。 駒箱の材質には、やはり銘木と呼ばれる御蔵島産の島桑や黒柿、屋久杉、欅材などが人気が高く有名です。 また、駒台と同じ素材の駒箱を揃える方もいらっしゃいます。






駒箱の製作は、盤の製作とは異なり「木工工芸師」の職人が製作することが多い棋具です。
駒箱は、駒が傷付かないよう釘を使用せずに製作されます。
箱の角を丸く加工した「隅丸」や蓋の天板を緩やかな曲線に仕上げた「天ムクリ」等、職人技が垣間見える技法で製作された駒箱もあります。
駒箱は、駒が傷付かないよう釘を使用せずに製作されます。
箱の角を丸く加工した「隅丸」や蓋の天板を緩やかな曲線に仕上げた「天ムクリ」等、職人技が垣間見える技法で製作された駒箱もあります。
隅丸

天ムクリ

駒箱に駒をそのまま入れると、箱の中で駒と駒が当たってキズ付いたり、盛り揚げ駒の漆が欠けたりする恐れがあるため、駒を保護する布製の「駒袋」というものが存在します。
駒袋には少し厚めの生地を使用し、巾着状の紐付きのものが用いられます。
また、出先で使用するために、駒袋に入れての持ち出し用にも使用されます。
駒袋には少し厚めの生地を使用し、巾着状の紐付きのものが用いられます。
また、出先で使用するために、駒袋に入れての持ち出し用にも使用されます。